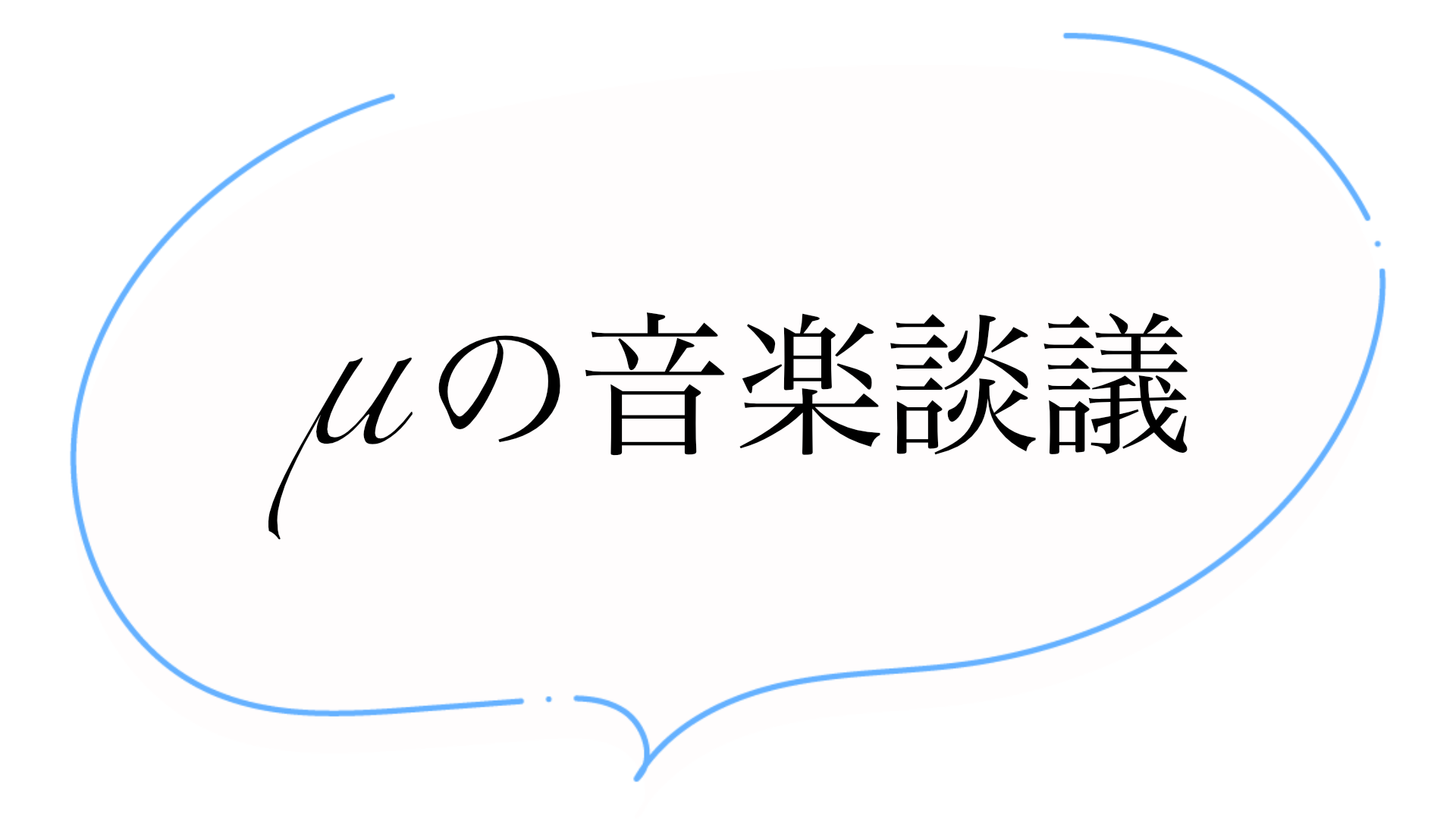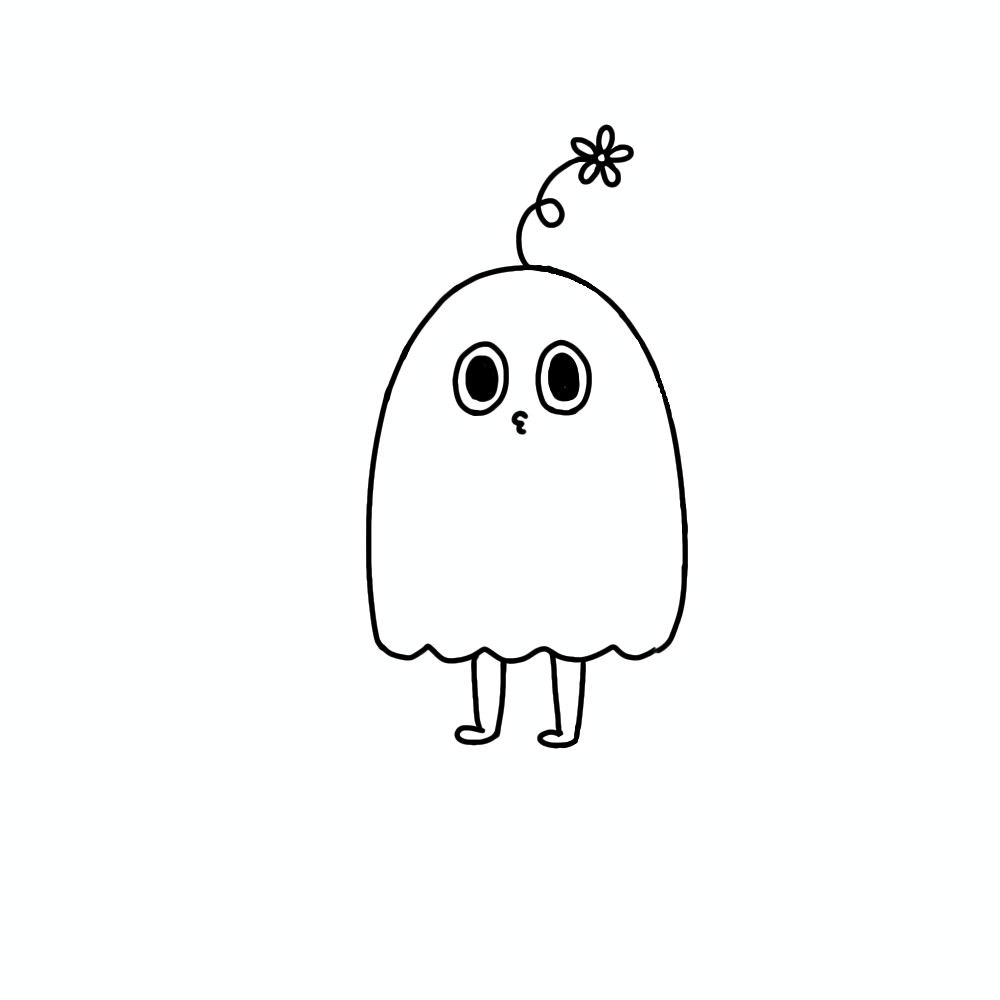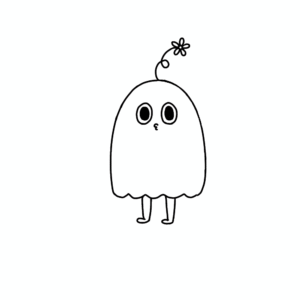
音楽制作では度々、「作曲」と「編曲」という言葉をよく見かけますよね。
なんとなく似ているけれど、「実際にはどう違うの?」と思っている人も多いはずです。
この記事では、「作曲」と「編曲」の違いをわかりやすく解説します。
専門用語はなるべく使わず、身近な例を交えながら説明していくので、音楽理論がわからなくても大丈夫です。
目次
作曲と編曲の違いとは?音楽制作の基本を解説
作曲と編曲の違いは、音楽制作の中でとても大切なポイントです。
完結にいうと、作曲は「曲のメロディやコード進行を生み出すこと」、編曲は「そのメロディをどんな楽器やリズムで演奏するかを決めて、曲を完成させること」と言えます。
たとえば、同じメロディでもピアノだけで演奏するのと、バンドで演奏するのでは曲の雰囲気が大きく変わります。
このように、作曲と編曲は役割が違うため、どちらも音楽作りには欠かせません。
違いを知ることで、自分がどの作業をしたいのか、どんなスキルが必要なのかがはっきりするでしょう。
作曲・編曲の定義と役割を整理
作曲と編曲の定義を整理すると、作曲は「新しいメロディやコード進行を考えること」、編曲は「そのメロディをどんな楽器やリズムで演奏するかを決めること」です。
作曲家は曲の骨組みを作り、編曲家はその骨組みに肉付けをして、曲をより魅力的に仕上げます。
たとえば、童謡の「きらきら星」は作曲家がメロディを作り、編曲家がピアノやバイオリンなどの楽器で演奏する形を考えます。
このように、作曲と編曲は音楽制作の中でそれぞれ大切な役割を持っています。
- 作曲:メロディやコード進行を作る
- 編曲:楽器の構成やリズムを決める
作曲と編曲の作業範囲を徹底比較
作曲と編曲は、音楽制作の中で担当する作業範囲が大きく異なります。
作曲は主に「メロディやコード進行を考えること」が中心ですが、編曲は「どんな楽器を使うか」「リズムやサウンドをどうするか」など、曲を完成させるための細かい部分まで関わります。
以下で、作曲と編曲の作業範囲や必要なスキルについて詳しく比較していきます。
作曲の主な作業範囲と必要なスキル
作曲の主な作業範囲は、曲のメロディやコード進行、曲の雰囲気を決めることです。
作曲家は、歌や楽器の主旋律を考えたり、どんな気持ちを伝えたいかをイメージしながら曲を作ります。
必要なスキルとしては、音楽理論の基礎知識や、楽器を使ってメロディを作る力、そしてアイデアを形にする発想力が挙げられます。
たとえば、ピアノやギターで鼻歌を弾きながらメロディを作る人もいれば、パソコンで音を並べて作る人もいます。
作曲は、曲の「土台」を作る大切な作業です。
- メロディやコード進行を考える
- 曲の雰囲気やテーマを決める
- 音楽理論の基礎知識が必要
- 楽器やパソコンでアイデアを形にする
編曲の作業範囲と求められる知識・技術
編曲の作業範囲は、作曲でできたメロディやコード進行をもとに、どんな楽器を使うか、どんなリズムや音色にするかを決めることです。
編曲家は、曲の雰囲気をより豊かにしたり、聴きやすくしたりする役割を持っています。
必要な知識や技術としては、楽器ごとの特徴や音の重ね方、リズムの作り方、パソコンで音を重ねる技術などが挙げられます。
たとえば、同じメロディでもピアノだけで演奏するのと、バンドやオーケストラで演奏するのでは、全く違う印象になります。
編曲は、曲を「完成品」に仕上げるための大切な作業です。
- 楽器の選び方や組み合わせを考える
- リズムや音色を工夫する
- パソコンで音を重ねる技術が必要
- 曲の雰囲気を豊かにする
同じ人が作曲から編曲までやるケース
最近では、作曲と編曲を同じ人が担当するケースも増えています。
特にパソコンや音楽ソフトが普及したことで、一人でメロディを作り、そのまま楽器やリズムを重ねて曲を完成させることが簡単になりました。
シンガーソングライターやバンドのメンバーが、自分で作曲から編曲まで行うことも多いです。
この場合、作曲と編曲の知識や技術の両方が必要になりますが、自分のイメージ通りの曲を作れるというメリットがあります。
- 一人で作曲・編曲を担当できる
- 自分のイメージをそのまま形にできる
- パソコンや音楽ソフトの活用がポイント
作曲と編曲の具体的なやり方・流れ
作曲と編曲のやり方や流れを知ることで、実際に音楽制作を始めるときのイメージがしやすくなります。
作曲は、まずメロディやコード進行を考えることから始まり、編曲はそのメロディに楽器やリズムを加えていく作業です。
最近では、パソコンや音楽ソフトを使って一人で全ての作業を行う人も増えています。
以下で、作曲と編曲の具体的な流れ等を詳しく解説します。
作曲の方法:メロディ・ハーモニー・コード進行
作曲の方法は、まずメロディを考えることから始まります。
メロディは、歌や楽器で一番目立つ部分です。
次に、メロディに合うハーモニー(和音)やコード進行を決めます。
コード進行とは、曲の土台となる和音の流れのことです。
作曲では、鼻歌や楽器でメロディを作り、ピアノやギターでコードを探す方法が一般的です。
また、パソコンやスマートフォンのアプリを使って音を並べる方法もあります。
自分の好きな曲を参考にしながら作ると、イメージがつかみやすいです。
編曲の方法:楽器パートのアレンジとサウンド作り
編曲の方法は、作曲でできたメロディやコード進行に、どんな楽器を使うか、どんなリズムや音色にするかを考えることです。
たとえば、ピアノだけで演奏するのか、ギターやドラム、ベースを加えるのかで曲の雰囲気が大きく変わります。
また、楽器ごとの役割(主旋律、伴奏、リズムなど)を決めて、全体のバランスを整えます。
パソコンや音楽ソフトを使えば、いろいろな楽器の音を重ねて試すことができます。
編曲では、曲の盛り上がりや静かな部分を作る工夫も大切です。
具体的には、イントロやサビ、間奏などの構成を考えたり音の重ね方を工夫したりします。
- 楽器の選び方や組み合わせを考える
- リズムや音色を工夫する
- 曲の構成や盛り上がりを作る
| 作業 | ポイント |
|---|---|
| 楽器パートの決定 | 曲の雰囲気やバランス |
| 構成の工夫 | 盛り上がりや静けさの演出 |
DTM・DAWを使った現代の音楽制作フロー
現代の音楽制作では、DTM(パソコンで音楽を作ること)やDAW(音楽制作ソフト)を使うのが一般的です。
まず、メロディやコード進行をソフトに入力し、次に楽器の音を重ねていきます。
ドラムやベース、ギター、ピアノなど、いろいろな音を自由に組み合わせることができます。
音の高さや長さ、リズムも細かく調整できるので、自分のイメージ通りの曲を作りやすいです。
また、録音や編集も簡単にできるため、初心者でも本格的な音楽制作が可能です。
最近は無料のソフトも多く、パソコン1台で作曲から編曲まで完結できます。
- パソコンやソフトで音楽制作ができる
- 楽器の音を自由に重ねられる
- 録音や編集も簡単
作曲と編曲が印象や雰囲気をどう変化させるか
作曲と編曲は、曲の印象や雰囲気を大きく変える力を持っています。
同じメロディでも、編曲によって明るくなったり、しっとりした雰囲気になったりします。
また、テンポやハーモニーの工夫によって、曲のイメージがガラリと変わることもあります。
ここでは、編曲による楽曲の変化や、具体的なアレンジ事例、原曲と編曲後の印象の違いについて詳しく解説します。
編曲による楽曲の変化とアレンジ事例
編曲は、同じメロディでも全く違う雰囲気の曲に変えることができます。
たとえば、童謡の「きらきら星」をピアノだけで演奏するとシンプルで優しい印象ですが、バンド編成にしてドラムやギターを加えると、元気でポップな雰囲気になります。
また、オーケストラで演奏すれば、壮大で感動的な曲に生まれ変わります。
このように、編曲は楽器の選び方やリズム、音の重ね方によって、曲の印象を大きく変える力があります。
プロの現場では、同じ曲を複数のアレンジで発表することも珍しくありません。
- ピアノだけ:シンプルで優しい
- バンド編成:元気でポップ
- オーケストラ:壮大で感動的
| 編曲例 | 印象 |
|---|---|
| ピアノソロ | 落ち着いた雰囲気 |
| バンド | 明るく元気 |
| オーケストラ | 壮大で感動的 |
テンポやハーモニーによる楽曲イメージの変化
テンポ(曲の速さ)やハーモニー(和音)の工夫によっても、曲のイメージは大きく変わります。
たとえば、同じメロディでもテンポを速くすると元気で楽しい雰囲気になり、ゆっくりにするとしっとり落ち着いた印象になります。
また、明るい和音(メジャーコード)を使うと前向きな気持ちに、暗い和音(マイナーコード)を使うと切ない気持ちになります。
このように、テンポやハーモニーの選び方は、曲の雰囲気を決める大切なポイントです。
- テンポを速く:元気で明るい
- テンポを遅く:しっとり落ち着く
- 明るい和音:前向きな印象
- 暗い和音:切ない雰囲気
まとめ
作曲と編曲には明確な違いがあります。作曲は「曲のメロディやコード進行を生み出すこと」、編曲は「そのメロディをどんな楽器やリズムで演奏するかを決めて、曲を完成させること」。
鼻歌等でメロディをつくることも立派な作曲といえるため、制作の上でハードルは低いといえるでしょう。編曲はそのメロディを完成品として仕上げる役割があり、膨大な楽器の知識等が必要になります。
もし音楽制作をしてみたい方はどういった知識が必要なのか確認してみてくださいね。