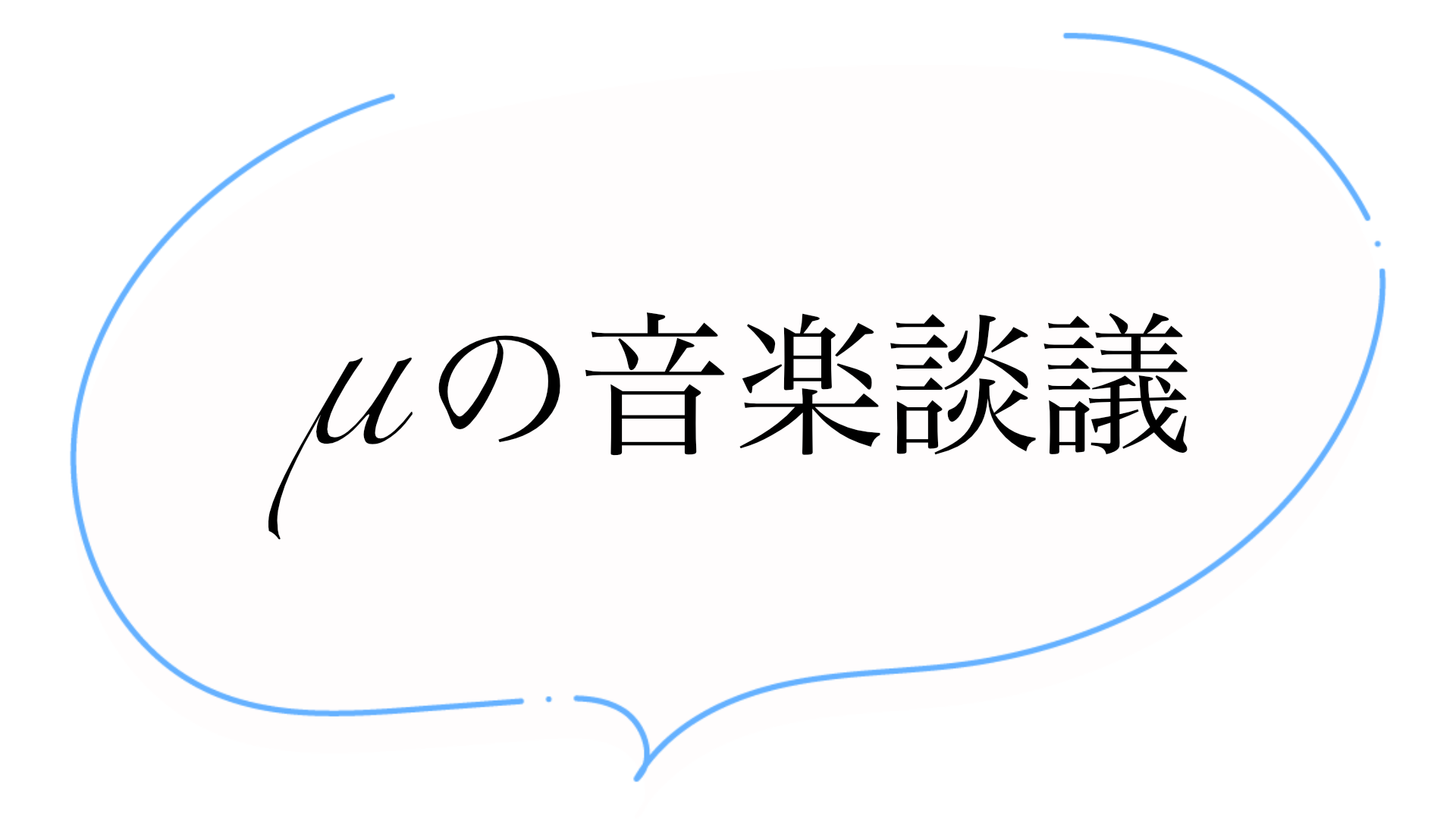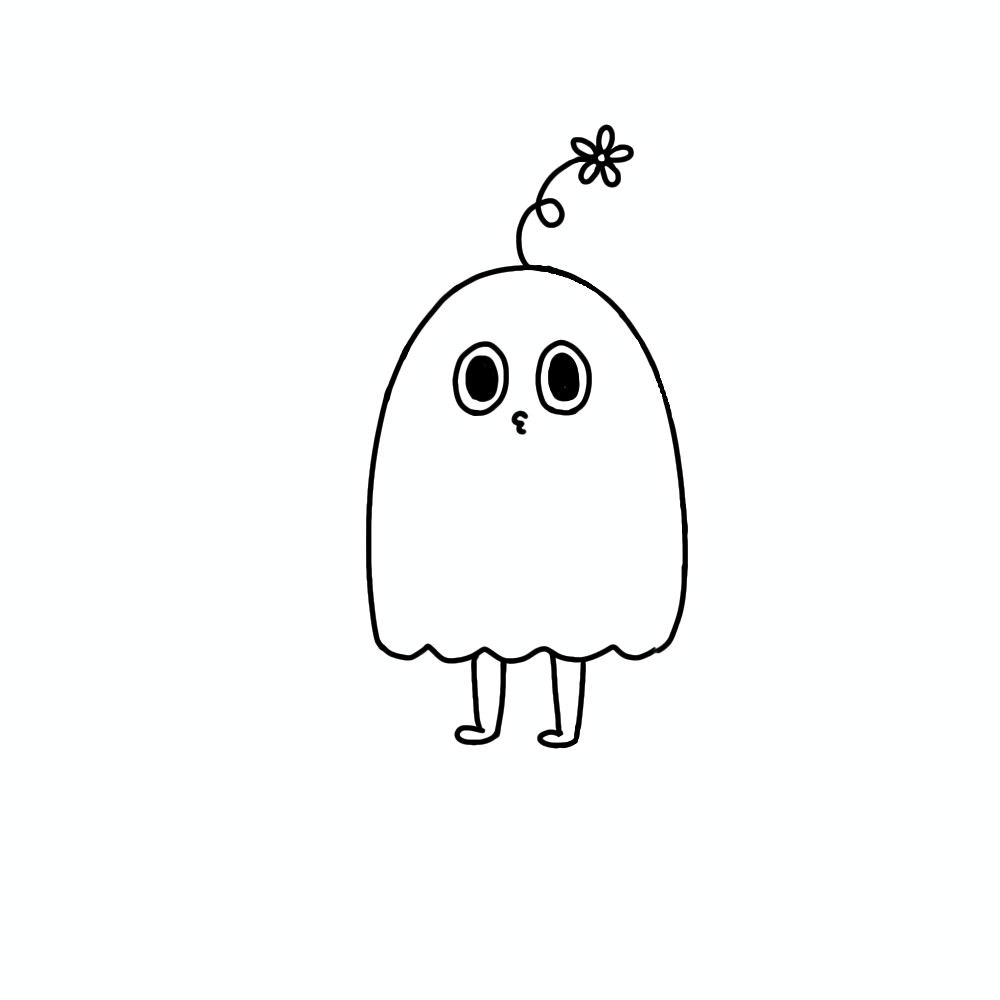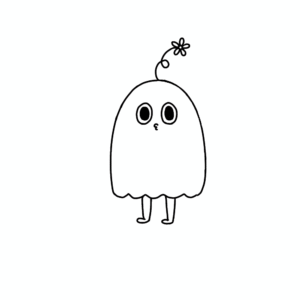
「作曲を始めたいけれど、音楽の知識も楽器もない…。本当に独学でできるの?」そんな不安を感じている方は多いのではないでしょうか。実際、独学で作曲を始めると、どこから手をつけていいのかわからず挫折してしまう人も少なくありません。
しかし安心してください。作曲は専門学校や教室に通わなくても、正しいステップを踏めば独学で十分に上達できます。 現に多くの有名ボカロPやDTM作曲家も、最初は独学からスタートしています。楽器ができないなんて人も多くいるのが事実です。
この記事では、初心者でも挫折せずに作曲を身につけるための具体的な方法を紹介します。必要な知識やツール、練習の進め方までを体系的に解説するので、今日からでも自分のメロディを形にできるようになるでしょう。
目次
独学で作曲は可能なのか?
結論、独学での作曲は十分可能です。独学での作曲にはメリットもありますが、注意点を押さえることが重要です。作曲を独学で行うメリットは以下です。
- 自分のペースで好きな時間に学習できる。
- 費用が抑えやすく、オンライン動画や書籍だけで始めることも可能。
- 自分の感性や個性を生かしやすい
一方で、注意しなければならない点もあります。例えば「何から学べば良いかが判断しにくい」「客観的なフィードバックが得にくい」といった壁です。
例えば、楽器経験が全くないAさんが、「まずは知識を本で読む」だけで始めたところ、何をどう練習すればいいか迷ってしまったとします。これに対して、Bさんは「毎日15分、曲を聴いて真似する」「5分だけメロディを記録する」という明確な習慣をつけ、半年後に短い曲を一つ完成させました。このように「明確な学び方」があるかどうかで“独学でできるかどうか”が大きく変わります。
つまり、独学での作曲は「自分で学べる」可能性が十分ある反面、学び方を誤ると挫折しやすいという構図が考えられます。
作曲を独学でする上でよくある不安
初心者が独学で作曲を始めるとき、よく抱く不安には次のようなものがあります。それらを先に知ることで、安心して学びを進められます。
- 楽器を弾けないけど本当に作れるの?
- 音楽理論が難しそうでついていけないかも
- 正しい練習方法がわからない
- 作った曲を人に聴かせるのが恥ずかしい
これらは初心者が感じやすい「独学作曲ならでは」の悩みです。ぜひ以下で解説していく内容を参考に不安の解消をしながら学んでいきましょう。
独学での作曲を続けられる人の共通点
作曲を独学で継続できている人には、いくつか共通の習慣があります。その習慣を真似することであなたも挫折しにくくなるでしょう。
どんなに才能があっても、習慣が身についていなければ上達は遅くなります。逆に、小さな習慣をコツコツ積み重ねた人ほど、半年後・1年後に大きな差が出ます。
継続できる人の習慣として、以下のようなものがあります。
- 毎日10分だけでも聴く・真似る時間を持つ
- 小さな「曲」や「フレーズ」を完成させて自分を褒める
- 「完璧」を求めず、まず形にすることを優先する
作曲を独学で続けられるかどうかは“才能”よりも“習慣”で決まることが多いのです。まずは小さなステップを毎日続けることから始めましょう。
独学での作曲に必要な道具と準備
作曲を独学で始めるために必要なものを確認していきましょう。
最低限必要なDAWと機材リスト
作曲を独学で始めるには、まず最低限揃えるべき道具があります。揃えればすぐに「作曲をする環境」が整います。
初心者がまず用意すべき道具を以下に挙げます。
- コンピューター(ノートでも可)
- DAW(音楽制作ソフト):無料版でも可
- ヘッドホンまたはスピーカー
- MIDIキーボードまたは簡易鍵盤(無しで作曲できる人もいます)
- 録音用マイク(歌や声を入れたい場合)
高価な機材を揃える必要はありません。まずは「できる環境」を作ることが肝心です。
無料のDAWと節約術
作曲はほとんど費用をかけずに始めることも可能です。工夫と選び方次第で、出費を抑えながら学びを進められます。
今は無料・低価格のソフト、試用版、オンライン教材が充実しています。それらを活用すれば、初期費用を大きく抑えつつ「とりあえず作ってみる」ことができます。出費が少ない分、続けやすくなり挫折のリスクも下がります。
音楽制作に必須といえるDAWソフトの無料版4選を以下で紹介します。
| DAWソフト | 解説 |
| Cakewalk SONAR | 無料DAWはまずはこれといえる、クセの少ないDAWと言えます。MIDIの打ち込みやオーディオの録音編集、外部プラグインの読み込み、ミックスなどDAWに求められる最低限の機能が無料で全部使えます。 最低限のインストゥルメントが付属しているため、とにかく何か制作を始めてみることが出来るという点で便利です。ダンロード&登録時に、BandLabアカウントを持っていない場合はアカウントの作成とログインが必要です。 |
| LUNA | 見た目が洗練されていてかっこよく、プロ仕様のDAWを制限なくすべての機能を無料で使うことが出来る、という太っ腹なソフトです。 LUNAのインストールは、UAアカウントを持っていない場合は登録し、UA Connectという専用ソフトウェアをインストールする必要があり、ややこしい点があるかもしれません。 |
| SoundBridge | 基本機能はほぼ網羅されており、日本語マニュアルが充実しているため、初心者の方でも比較的触りやすいのではと思います。 コンプレッサーやリバーブ、ディレイ、コーラスなど基本的なエフェクトが内蔵されており、オーディオトラックにカラオケ的な音源やギターなどのバッキングを入れ、ボーカルを録って、簡単にリバーブやコンプで整えるとそれなりの歌ってみた作品みたいなものは作れてしまうかと思います。 ただ、無料版では機能制限があり「最大トラック数が10個まで」となります。また、MIDIインストゥルメントは用意されていないので、VSTプラグインを自分で用意する必要があります。 |
| Reaper | 正確には60日の無料試用版が配布されていているのですが、60日を超えても無料で使い続けることができるようです。 動作が軽く、PCのスペックが気になる方は検討してみてはいかがでしょうか。他の無料DAWと同じく、オーディオもMIDIも扱え、VSTプラグイン対応でインストゥルメントやエフェクトを追加していくことも可能です。基本的な機能は網羅されています。 |
独学で始める際には「まず無料・安価な手段から始めて、インターネットの無料講座や動画を活用しつつ、必要になったら少しずつ機材をグレードアップする」この方法でも作曲は可能です。金銭面が気になる方は「お金をかけずに作ってみる」ことをおすすめします。
学習環境の整え方(時間・習慣)
作曲を独学で成功させるには、環境を整えることが大切です。具体的には、学習時間を確保し習慣にする仕組みをつくることです。環境を整えるためのポイントは以下の通りです。
- 「毎日15分」など短くてもいいので決まった時間を設ける。
- 使用するパソコンや鍵盤を「曲作り用の席」に固定する。
- スマホの通知をオフにして集中時間をつくる。
- 週末だけ長めの時間を確保してまとめ練習する。
独学での作曲は自分との勝負です。道具を整えたら、次は「いつ・どこで・どう始めるか」を決めてしまうことをおすすめします。
作曲を独学でする上での学習順序
独学で作曲を最短で上達させるには、聴く→真似る→作るの順番で学ぶことが最も効率的でしょう。
いきなり「オリジナル曲を作ろう」としても、音の並べ方や構成の基礎がわからず、途中で止まってしまいます。まずは音楽の“型”を知ることが大切です。例えば次のようなステップを踏むと上達が早くなります。
- 好きな曲をよく聴く(リズム・メロディ・コードを意識)
- 聴いた曲を真似して作る(そっくりでもOK)
- 慣れてきたら少しずつ自分のアレンジを足す
この流れで学べば、耳で学んだ知識がそのまま“作曲力”になります。「聴くこと」も立派な学びです。まずは真似てそこから自分の音を見つけていきましょう。
短い曲でもまずは完成させることが重要
独学での作曲の際、まずは「短くても完成させる」ことを意識しましょう。
長い曲をいきなり作ろうとすると、途中で混乱してしまいがちです。短い作品を完成させるほうが「達成感」を得られ、学びが早くなります。次のように練習するのが効果的です。
- まず「10秒〜30秒のメロディ」だけ作る
- 1週間に1曲を目標にする
- 完成したら必ず保存して聴き返す
- 気に入ったものをつなげて1曲にする
独学では“短くても完成させる”ことが成功の第一歩です。量を重ねることで質が自然に上がっていきます。
理論は必要なタイミングで学ぶ
音楽理論は「作りながら学ぶ」のが一番効率的です。
理論だけ先に学んでも、実際の曲作りでどう使うのかピンとこない場合があります。理解が浅くなり、覚えづらくなってしまうためです。次のように段階的に学ぶのが理想的です。
- 最初はメロディを自由に作る
- 次に「なぜこの音が気持ちいいのか」を調べる
- 必要になったときに「コード」や「スケール」を勉強する
このやり方なら、理論が“使える知識”になるでしょう。独学での作曲では、理論を焦らずに「作って→調べて→理解する」順番で身につけることがおすすめです。
独学で作曲をする際に押さえるべき音楽理論の基礎
独学で作曲をする際にまず知っておきたい理論があります。「キー(調)」と「ダイアトニックコード」です。これらは“曲の土台”であり、どんな音を使えば自然に聞こえるかの基準になります。
例えば「ハ長調(Cメジャー)」のキーでは、使われる音がC・D・E・F・G・A・Bの7つです。この中の音だけを使えば、どんな順番にしても心地よい響きになります。
その7つの音に対応するコードが「ダイアトニックコード」と呼ばれます。初心者のうちは、次の3つを使うだけでも十分です。
- C(ドミソ)
- F(ファラド)
- G(ソシレ)
この3つを組み合わせるだけでも曲が作れます。「キー=使う音のグループ」と覚えるだけでも大きな前進です。
基本のコード進行を真似しよう
コード進行からの作曲は最も手軽で良いメロディが生まれやすいでしょう。また、難しい進行を最初から使うより、よく使われるパターンを覚えた方が耳にも馴染みやすく、聴きやすい曲になります。
- C→G→Am→Em→F→C→F→G(有名な「カノン進行」)
- Am→F→G→C(小室進行)
- F→G→Em→Am(ポップスによく使われる王道進行)
例えばJ-POPやボカロ曲の多くも、これらの進行をもとに作られています。まずは1つの進行でメロディを作り、次に別の進行で試すと感覚がつかめます。「コード進行を真似して学ぶ」が上達の近道です。
独学でメロディを作る具体的な手順
作曲では「完璧なメロディを作ろう」とせず、まずは思いついたものを残すことが最初の一歩です。
まずは鼻歌→録音の習慣
メロディ作りは「鼻歌から始める」のがいちばん自然です。声は最も身近な楽器だからです。難しい理論を考えずに、思いついたメロディをその場で形にできます。
- お風呂・散歩中に口ずさむ
- スマホで録音する(思いついた瞬間に)
- 後から聴き返して気に入ったものを選ぶ
この習慣を1週間続けるだけで、メロディの“引き出し”が増えていくでしょう。
良いメロディのチェックリスト
独学での作曲でも、良いメロディかどうかを自分で判断することができます。次の項目で自分の作った曲を客観的に見てみましょう。
- 一度聴いて覚えやすいか
- リズムが単調すぎないか
- 高すぎる・低すぎる音が続いていないか
- 最後まで自然な流れで終わっているか
- 自分で聴いて「また聴きたい」と思えるか
これらを意識するだけで、完成度が大きく上がります。良いメロディとは「聴く人が気持ちよく感じるメロディ」です。耳を鍛えながら少しずつ磨いていきましょう。
メロディが思いつかないときは下記の記事も参考にしてください。
独学で作曲をするときに挫折しないモチベ管理法
モチベーションを保つコツは、小さな達成を積み重ねることです。
- 毎日10分だけ触る
- SNSに1フレーズ投稿する
- 月に1曲、完成させる
また、他人の曲を真似て作る「コピー練習」も良い刺激になります。作曲家の多くは「模倣から始まる」と語っています。
独学で作曲をするにあたってよくあるQ&A
Q1:楽譜が読めなくてもできますか?
はい、できます。今は耳コピやソフトのピアノロールで十分対応可能です。
Q2:楽器が弾けないとダメ?
必要ありません。マウス操作だけで曲を作る人も多いです。…とはいっても楽器が弾けると曲作りに有利と個人的に感じます。
Q3:独学でプロを目指せる?
十分可能です。YouTubeやSNSで活動している独学作曲家は数多く存在します。
作曲を独学でするにあたってのまとめ
作曲は専門学校や教室に通わなくても独学で十分に上達できます。 現に多くの有名ボカロPやDTM作曲家も、最初は独学からスタートしています。ただ、継続や時間管理、努力は誰よりも必要なのが現実です。
- 好きな曲を真似てみる
- 1分の曲を作る
- 完成したらSNSに投稿する
この3つを繰り返すだけでも、作曲のスキルは確実に上達します。独学でも正しいステップと継続があれば、誰でも自分の音楽を形にできます。